2023/02/24
言語・思想・哲学等の書籍の買取 【55冊 5,680円】「英詩のわかり方」2007年、研究社
今回は言語学や思想、哲学などに関する書籍の買取をいたしました。以下に特に良い査定額をお付けできたものを紹介いたします。
「談話と情報構造」
「A Prosodic Model of Sign Language Phonology (Language, Speech, and Communication)」
「Mathematical Methods in Linguistics (Studies in Linguistics and Philosophy) (Studies in Linguistics and Philosophy, 30)」
「明解言語学辞典」
「英詩のわかり方」
「カムイユカラでアイヌ語を学ぶ」
「言語研究のための統計入門」
「ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に働くための本」
「Cognitive Linguistics: An Introduction」
「国際学会English スピーキング・エクササイズ口演・発表・応答 音声CD付」
などなど。
さて、こちらの記事を読んでいらっしゃる方の大半は当店の買取HPがリニューアルしたことにお気づきかと思います。当店にて「買取できるもの・買取できないもの」 には特に変更はございませんが、以前より画像等を増やし視認性を上げたつもりでございます…!「ノースブックセンターではどんなものを買い取ってくれるの?」という疑問を持たれましたら、上記リンク先をご参照いただけますと幸いです。
また、当店の買取サービスの強みをまとめた「ノースブックセンターの10の特徴」のページもリニューアルしています。「他の古書店とどう違うの?」と比較検討されたいとき、ご参考にしてください。
高額査定となったお品の内容ですが、上記の「~10の特徴」にも書かせていただいているように当店では洋書(英語のみ)も買取歓迎しており、今回も洋書が何点か入っています。英語で書かれた論文で邦訳がまだ出版されていないことは、しばしばあります。専門的に研究されている方にとってそれが重要なものである場合、その原書にあたる必要があるため洋書の専門書には一定のニーズがあります。当店では専門書を多く扱っていることから、再販することも得意としております。もう使わない洋書の専門書、「マニアックすぎて売れないかも…?」「洋書というだけで他の古書店では買取を断られてしまった」という不安や苦い経験をお持ちの方、もし使わないものがあれば是非、当店にお譲りください!次の必要とする方につなぎます。
では、いつものように気になる一冊をピックアップしたいと思います。
今回ご紹介するのはこちら。
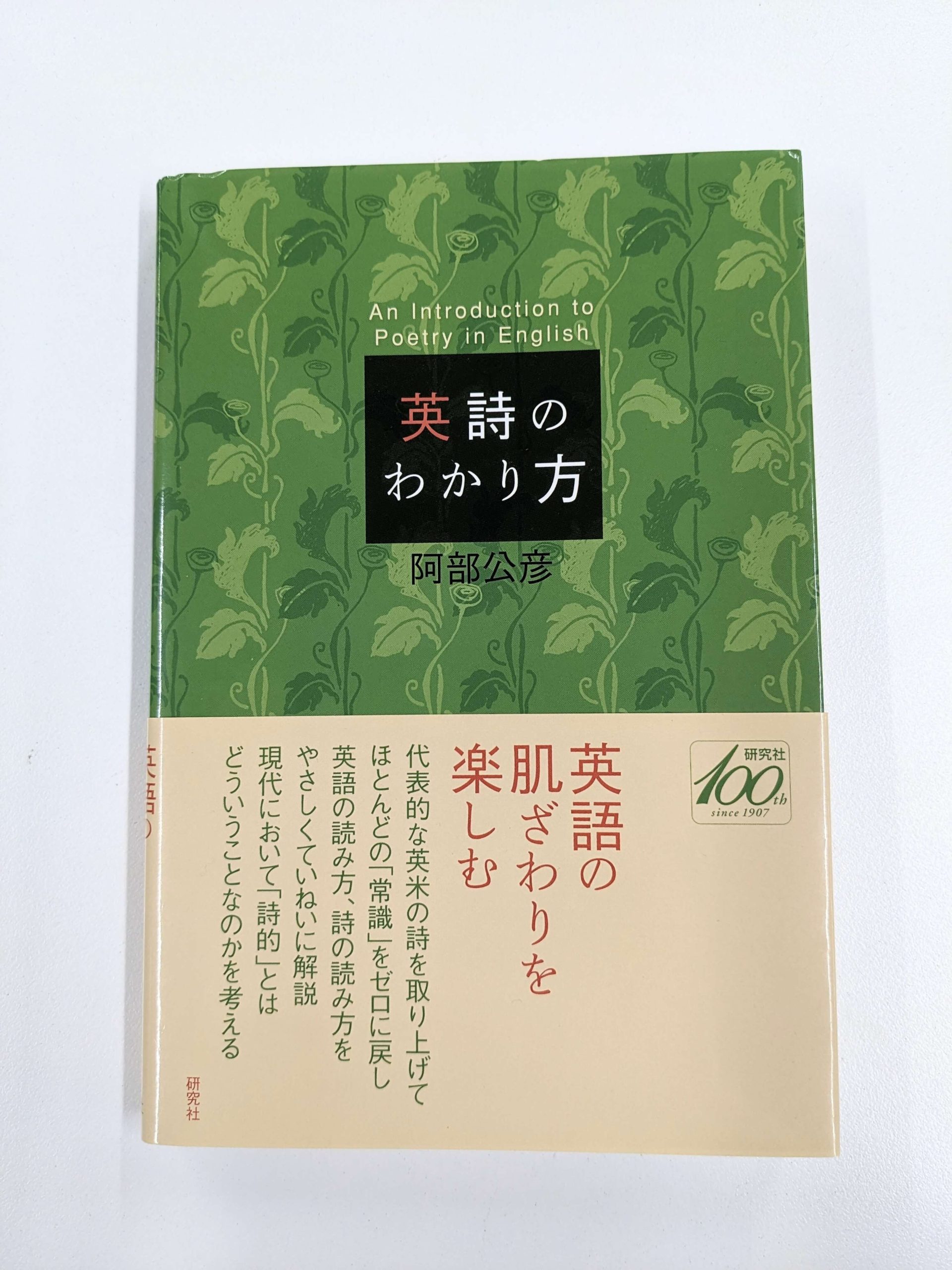
「英詩のわかり方」2007年、阿部公彦 著、研究社
です。皆様は英語で書かれた詩を鑑賞することはお好きですか?
私はと言えば、正直を申しますと、好き・嫌い以前の問題です。鑑賞の仕方が分からないんです…。
その理由の1つ目には私自身の語彙力のなさがあり、また2つ目には英詩では(私から見れば)変な場所で改行されているため主語と述語の関係性すらも見失ってしまうこと、また、3つ目には詩の詠まれた背景や文化が分からないせいで、よしんば意味が掴めても詩人のテンションが理解できなかったり…と、数え上げるとキリがありません。故に、英詩からは遠い人生を歩んで参りましたが、魅力的な題名と魅力的な厚み(笑。全237ページです。)に惹かれて挑戦してみた次第です。
目次
魅力的なタイトルと目次
本書でまず目を引くのは、先程も書いた「魅力的な題名」です。「わかり方」ってなんだか良くないですか?「味わい方」や、「読み方」ではないのです。「味わい方」は少し敷居が高い感じがします。「読み方」では最低限の語彙の理解で終わってしまいそうな感じがしますし、なんだか少し硬い。「わかり方」だと、読後に「あ・・・なんかちょっと分かった気がする。」くらいの感想が得られそうな優しさ・易しさが漂いませんか?あえて「わかり」が平仮名なことの効果もあるのでしょうね。
次に気になるのが各章のタイトルです。本書目次より以下に記載します。
序章 あらゆる詩は外国語で書かれている
第1章 英詩は嬉しい
第2章 なぜ英詩は声に出して読んではいけないのか
第3章 英詩は失敗する
第4章 英詩は問答する
第5章 なぜ英詩は偉そうに決めつけるのか
付録 英詩の韻律
参考図書
おわりに
いかがでしょうか?意外なものも結構ありますよね。第2章などは見た瞬間「えっ!?」となりました。本書でも触れられていますが『声に出して読みたい日本語』などのヒットから、声に出して朗読するのが、むしろ推奨される読み方なのかとすら思っていました。ましてや、英詩で有名なソネット形式(←鑑賞音痴でも知識だけはある)は脚韻を踏んでいるわけで、朗読してこそ良さの生まれるリズムが採用されているのではないのでしょうか??
とりあえず、読んでみました
まず、序章の「あらゆる詩は外国語で書かれている」ですが、ここでは何も「日本語で書かれているものは詩じゃない!」なんて乱暴なことを言っているわけでは、もちろん、ありません。阿部氏(以下、著者)は、テクストには他者性がいつも存在していることを指して、こう発言しているのです。詩に綴られた言葉の中に身を置くことは、他人の世界の中に浸ることに相違ありません。その他人の家に足を踏み入れたような感じと、外国の見知らぬ言葉に出会うという未知との遭遇感を類似の体験だと説明するための比喩でもあります。
また、この章では他言語→日本訳した際、詩には繊細なニュアンスの違いが出てしまう難しさを荻原朔太郎の「恋を恋する人」を例として説明しています。この例えは詩鑑賞音痴者にも非常に分かりやすかったです。やはり英詩は英詩のまま鑑賞すべきなのね!と納得したところで1章に入ります。
先程、私は「詩人のテンションが理解できない」ことが英詩を敬遠する理由の1つだと書きましたが、1章ではまさにその部分に触れています。英詩って「God!」とか「Oh!」とか言っているイメージがあったのですが、まさにそんな詩たち(ワーズワス『序曲(The Prelude)』より出だし部分)』/ホイットマン『ぼく自身の歌 24番( Song of Myself)』/シェリー『西風に寄せるオード(Ode to the West Wind)』) が紹介されています。本書で紹介された作品群を見て、「おおぉぉ…なんか叫んでる…」とちょっと感情の起伏少なめの私は、やはり、ひいてしまったのでした。
その一方で、本書では原詩と共に著者オリジナル訳が掲載されており、それと合わせて詩のテクニック的な理解のポイント、その詩人が当時どのような思想的潮流の中で、どのような作品作りを目指していたのか、どのような人生を歩んだのかなどの解説が充実しています。それによって、苦手だったはずの英詩もぐいぐいと面白く読めるので不思議です。本書が入門書であり、比較的誰にでも分かりやすいように平易な言葉で書かれているところも大きいと思います。
そして、何より助かるのが、その英詩初心者の「ひいてしまう」感じを著者も共有してくれていることでしょうか。英詩の世界に「分からないなら分からないなりに、とりあえず受け入れてみよう」というスタンスから入ることを許容してくれるので、「そうか、じゃあ、次の作品も読んでみるか」という気にさせてくれるのですね。
そして、先程も触れた第2章「なぜ英詩は声に出して読んではいけないのか」ですが、ここでは1章で紹介された感情爆発系の作品とは対照的に、繊細さが持ち味の作品(プラス『レイディ・ラザルス(Lady Lazarus)』『ダディ(Daddy)』/ヒューズ『思考狐(The Thought-Fox)』『パイク(Pike)』『一撃(The Shot)』)たちが紹介されています。ここで紹介されているシルヴィア・プラスとテッド・ヒューズは元夫婦です。プラスはヒューズの女性関係から精神が不安定になり離婚、その後ガスオーブンに頭を突っ込んで自殺するという壮絶な最期を迎えています。この章ではそういった彼らの不安定さが描写された作品から、声に出すだけで壊れてしまう、そんな脆く儚い詩の味わいについて解説されます。
第3章は2章を引き継いだような内容だという印象を持ちました(「口承起源説」について言及しつつ、紙に書かれたものとしての現状を鑑みた詩のあり方を考えるべき、とする。)。この章では、20世紀に入り伝統的な詩の形式から解放された新しいスタイルの作品が紹介されています(ディキンソン『私は葬式を感じた 頭の中で(I felt a Funeral,in my Brain)』/ロレンス『蛇(Snake)』/ヒーニー『掘る(Digging)』) 。
第4章は英詩の中でよく見られるスタイル、「問答形式」について触れています。その形式が採用される背景として、キリスト教布教の際に用いられた問答形式のテクスト=カテキズムの存在に触れられています。「キリスト教は言葉を重視する宗教」であり、「預言者たちを通して伝えられる神の言葉をいかに受け取るかが信仰のあり方を決め」るため、「問答形式は言葉のやり取りを通して権力の所在を鮮明にするのに、まさにぴったりの型なの」だと述べられています(「」部分、本書p170より引用)。この章ではそんな背景もあり、キリスト教の宗教色が出ているもの、はっきりとした問答形式をとってはいないが詩人が内なる自分へ問いかけを発するものなど、いくつかの作品が紹介されています(ミルトン『私の目の光はどうなったのか(When I consider how my light is spent)』/シェイクスピア『ソネット18番(Sonnet 18)』/トマス『手(The Hand)』/ラーキン『日々( Days)』『お次、どうぞ(Next,Please)』/イエイツ『湖のイニスフリー島(Tha Lake Isle of Innisfree)』)。
第5章は「なぜ英詩は偉そうに決めつけるのか」ですが、第4章で取り上げられたキリスト教的な権力構造の影響を受けた英詩において、言葉短く断定的に書かれることの効果がまとめられています(p197~p198)。また、本書の最終章らしく、今まで著者が述べてきたことを大きくまとめている章でもあります。すなわち、序章で触れた他者性にも通じるところですが、「分からないなら分からないままでも良い」という、許容とも、突き放しとも言えるユルさが再度強調されます。この章において、著者が本書の中でも強めに主張したいと述べた「詩は独り言で語ることを許されている」(p203)という部分は第2章とも根を同じくしているとも感じます(第5章ではディキンソン『名声は蜂(Fame is a Bee)』/スティーブンス『青いギターの男 第22歌(Tha Man With a Blue Guitar,XXⅡ)』/エリオット『四つの四重奏』より「バーント・ノートン」(Burnt Norton,Fout Quartets)/シェイクスピア『ソネット94番(Sonnet 94)』が取り上げられています。)。
まとめると
ざっと本書を通読してみて、やはり救われたのは詩の鑑賞にあたっては「分からないものは分からない、でも、琴線に触れるものがあるかもよ?」「「っぽさ」で読んでみよう(序章、及び「おわりに」より)」という読者側の自由度を認めてくれている部分でした。
もちろん、とんでもなく的はずれな鑑賞をしてしまうのでは詩人にとっても、読者本人にとっても不幸なことであるでしょうから、こういった入門書を入り口に「わかり方」を「わかる」のは大事なことだと思います。
そして、これは本書の中には書かれていなかったことですが、詩の鑑賞に必要なのは、短い詩という形式に詩人が厳選して使用した言葉には無駄がなく、「その言葉である必然性」に敏感に反応する感性を磨くことなのではないかな?という感想も持ちました。本書タイトル・各章のタイトルからも、著者には詩研究者としての高性能言葉センサーが搭載されているのを、ひしひしと感じます。言葉に敏感になるセンスを磨くには…やはり、時間がかかるけれども、より数多くの詩に触れてみるのが早道なのかな、と覚悟が決まりました。
・・・とはいえ、一人で英詩の原文にいきなりアタックするのはまだ難易度高めなので、著者が本書の続編を出されることを期待しています。すでに本書でも有名な作品がいくつも紹介されていますが、まだ私の知らない詩人なんてたくさんいるでしょうから。阿部先生、よろしくお願い致します!(笑)
先にも書いたように、本書はあくまで入門書なので韻律(英詩の持っているリズムや韻)についての専門的な知識は省略されて(本書ではp227から2ページのみにまとめられています。)いますが、もっと読みたい人向けには参考図書が巻末に挙げられていますので、私より英詩鑑賞上級者の方も楽しんで読める一冊なのではないかなとも思います。いずれにせよ、オススメです。
今回も良書をたくさんお譲りいただき、ありがとうございました!
スタッフN




