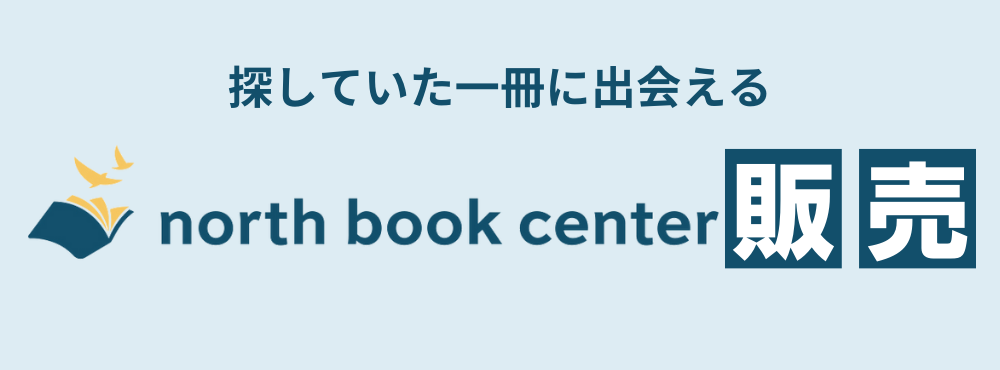2025/11/07
社会学・哲学関連書籍の買取
買取日記ジャンル
今回は、思想・社会理論を中心とするコレクションをお譲りいただきました。
日常や空間、言語、権力、文化など、人の営みを多角的に読み解く哲学・思想書が多く含まれていました。
その中から特に気になった一冊を紹介していきます。
目次
本書の概要
『日常的実践のポイエティーク』 ミシェル・ド・セルトー
※ポイエティーク:制作や発明、詩的な創造といった「制作のプロセス」そのものを研究対象とする学問
読むこと、話すこと、書くこと、住むこと、料理すること……、これらの行為は、さまざまな営為に満ちた「戦術」(セルトー 1980=1987)的な実践的行為である。そこで描き出される場とはすなわち、ある権力の場として抑圧的に管理がなされているような、あらかじめ用意された舞台上の演出ではない。
かつて、ミシェル・フーコーは近代的な抑圧の装置を「規律社会」(フーコー 1975=2020)という語で示した。しかしながら、フーコーの予見通り、この社会は短命であった。それに取って代わる権力作用が如何様のものなのか。あるいはまた、「規律社会」が監視カメラなどのように新たなテクノロジーによってわずかに残存しているかどうかは、セルトーにとってもはや関係がない話である。
これらの行為は、セルトーが言うには「日常的行為の実践」(セルトー 1980=1987)であり、権力の場に曝されながらも、「なんとかやっていく」(セルトー1980=1987)行為であった。本書の主眼はすなわち、この実践的な行為を権力者の下に帰するのではなく、主体の闘争の場で生ずる駆け引きを描きとるような、フーコーの分析を裏返すものである。さながら、巨大な摩天楼のビルディングから俯瞰する都会の景観ではなく、そのすぐ足元に広がる路地の上で行われている主体の闘争の駆け引きの場を緻密に分析したものであった。
この行為の創造性はしかるに、上部構造を決定づけるような、革命主体としての下部構造ではなく、いままでも、そしてこれからも、この構造に支配されながら生きていくような主体が選択する、銘々の独特な人生の肯定の仕方であった。これらは権力者の下で白昼堂々と行われるものでありながらも、隠密形態を取っているのだ。
さて本稿では、本書の要である歩くことに関する第7章に絞って、本書の要約と考察を行うこととする。
第7章 都市を歩く
「世界貿易センターの一一〇階からマンハッタンを見る」(セルトー 1980=1987:199 原文強調)。摩天楼から見下ろす大都会の景観は、「まなざしの下、巨大な人群れははたと動きをとめてしまう。その人群れはテクストの群れに変わり、そのテクストのなか、ものみなすべてが一致しあう。野望と落魄の両極も、人種やスタイルのすさまじい対立も、つい昨日建てられたばかりなのに早やごみ捨て場と化したビルディングの数々と、空間を埋めつくして沸きかえる昼の町のにぎわいとのコントラストも、渾然一体、みなひとつに溶けあってしまう」(セルトー 1980=1987:199)。
本章はこのような語り口から始まる。超高層のビルが立ち並ぶ都会の景色は、こんにちの私達にとって、すでに日常の見慣れた風景と化してしまった。その理由は、情報が加速度的に圧縮された結果であるために、虚妄のメディアを通して、既視感のあるものへと置き換えられてしまったのか。あるいはまた、都市空間の模倣が相次いで表出したせいだろうか。いずれにせよ人はみな、この「消費と生産の過剰からなる巨大なレトリック」(セルトー 1980=1987:200)から見下ろす景観に対して、——たとい、セルトーの時代から半世紀経った現代であろうとも、——何かしら歓びのようなものを感じる。
全体を見るときの歓び、すなわち、かつてない規模のこのテクストの全貌をみはるかすこの歓びは一体如何様のものなのか。セルトーにとって、この歓びとは、都市を支配する高みのようなものであった。いまひとたび地上に降りてみるのならば、街路に縛られた差異のひしめき合いが、現にある場所から脱出することを望むように促す。しばしばこれを大衆からの脱却と呼ぶものの、しかしながら、それは「見る者」の「知の虚構」(セルトー 1980=1987:201)であった。
そうした「見る者」の巨視的な様態とは対照的に、街路の上で日々行われている都市の日常的な営みがある。この日常的な営みの形態とはすなわち、街路に縛られつつ、その当の街路を歩く者たちのことである。歩行者たちの身体は、つねに街路の中にありながらも、その中でいかにして抵抗するかという画策がなされているのである。
ここでいう「歩く者」たちは、つねに街路をあるがままに闊歩する者たちのことであり、その行動は誰もが予測しえないテクストを完成させるのである。ともすれば、その歩行者の描くテクストとは畢竟、すでにあらかじめ用意されたルートに沿って行われる行為のそれではなく、「都市という「テクスト」の活字の太さ細さに沿って動いてゆく」(セルトー 1980=1987:202)ものである。
したがって、「これらのエクリチュールの網の目は、作者も観衆もない物語、とぎれとぎれの軌跡の断片と、空間の変容とからなる多種多様な物語をつくりなしてゆく」(セルトー 1980=1987:202)のである。これらは無限の選択肢を生み、たえざる逃走によって、ビルディングの上から覗き見る視点を無きものにしてしまう。
無きものにされる一大パノラマの景観とは、つねにある固定された地点からの視座に縛られている。その鳥瞰される都市は「ものみなすべてが一致しあう」ような、雑多なテクストをある一つの次元に押しとどめてしまうのである。だがしかし、都市の街路に縛られる者たちは鳥瞰する者とは反対に、視点の固定化は行われず、雑多なテクストを読むどころか、そのテクストを作り出す主体として都市と関わっている。したがってこの諸行為は、ある種の固有で多種多様な物語を作るといってよいだろう。
*
こうした「視による知の非空間―ユートピア」(セルトー 1980=1987:203)は、都市の群衆が織りなすテクストを分節化しようとする企図を抱き続けている。このようなフィギュールの裁断はしかるに、「都市と概念の結託」による都市の計画化ないしは、「分節化するすべを知り、実際に分節化しうるということなのである」(セルトー 1980=1987:204)。
この都市計画的な意味で創設される「都市」は、三つの操作可能性によって規定されている。
- ある固有な空間の生産。つまりは、合理的組織化をはかることによって、この空間を脅かす恐れのあるものを抑制すること(セルトー 1980=1987:204)。
- 伝統に根差した捉えがたく頑迷な抵抗に対する、非―時間、あるいは共時的システムの代置。すなわち、歴史の不透明性をもたらす使用者の戦術に抗して、データを同一平面上に並置し、一義的な戦略を行うこと(セルトー 1980=1987:204)
- 匿名の普遍的主語=主体の創造。したがって、主語=主体であるほかならぬ都市は、離散している集団や個人など、もろもろの機能と述辞のことごとくを都市という主語=主体に帰属させることが可能となる。(セルトー 1980=1987:204-5)
とどのつまり、ここでいう「都市」とは、現実的主体に対してある神話化の作用をもたらすのである。みずからの戦術的な実践は、本来ならば可能性の条件をもたらすものであるが、この神話化の作用によって、進歩や時間を特権化させてしまい、空間そのものを忘却させるのである。
しかしながら、この「都市」に帰属させられる諸々の人は、たしかに帰属を強制されつつも、生きていることは確実であろう。セルトーの一節を引用しよう。
わたしは、規律からははずれているが、といって規律の力がおよぶ領域の外にあるのでもないような手続き——さまざまなかたちをとりながら、抵抗をつづけ、狡智にたけて頑迷な手続き——のいくつかをあとづけてみたいと思う。それらの手続きは、われわれを日常的実践の理論へ、生きられた空間の理論へ、そして都市の思いがけぬ身近さをあらわにしめす理論へとみちびいてくれるにちがいない。
(セルトー 1980=1987:208)
*
歩行者たちの「足どり」(セルトー 1980=1987)の運動は、数えられず、独自のものである。これらは、空間細工を作り、それがあってこそ都市が真に都市たりうる現実的システムであり、物理的には収納不可能なものだ。
歩くという行為は、痕跡を書き写したりして、都市地図の上に書き直すことができないわけではないが、その歩行のフィギュールには太いものも細いものもあり、すでに通りすぎていったものである。それゆえ、都市地図への再編成は、人の行動を読みうるものへと変換してしまい、世界に現存しているという主体のありようを忘却させるに至る。
なるほど歩くという行為は、ある発話行為と置き換えることが可能であることを発見したセルトーに対して、単にフーコーの権力論を裏返しただけに過ぎないといってしまっては、本書の慧眼たる部分を見逃してしまうことになるだろう。
歩行はセルトーいわく、三重の発話的行為の機能を果たしている。第一に、ちょうど話し手が言語を自分のものにして、身につけるのと同様に、歩行者が地理システムを自分のものにするプロセスである。これは現存性に係る(セルトー 1980=1987:210)。第二に、ちょうどパロール行為が言語の音声的実現であるように、場所の空間的実現である。これは不連続性に係る(セルトー 1980=1987:210)。第三に、ちょうど言葉による発話行為が「話しかけ」であって、話し手と「相手をむかいあわせ」、対話者どうしのあいだにいろいろな契約を成立させるように、相異なる立場のあいだで交わされる様々な動的形態の関係を含むものである。これは「交話性」に係る(セルトー 1980=1987:210)。
歩き方のレトリックは、すなわち不連続性を如実に体現したものである。じっさいに様々な価値の様態による「足どり」は、たとえば断言、疑い、口ずさみ、踏み外し、順守といった多様性を生じさせる。この多様性は、まったきグラフ上の線や地図上に書き表すことは不可能なのである。たとい一望監視的な空間であろうとも、その空間に細工を加え、その空間を相手どって戯れることが歩行者のレトリックには可能だ。したがって、その身振りは、合理的規則のそれに組織化された一員からエトランジェなものでもなく、かといって迎合し順応するものでもない。そこでの身振りは、なんかしらの影と両義性を生み出していき、自分だけのさまざまな参照や引用を差し挟んでいくのだ。
道ゆく人びとの歩みぶりは、ある時にはそれ、またある時には曲がりくねって、「言いまわし」や「文彩」にも似た紆余曲折をしめしている。歩行のレトリックが存在するのである。
(セルトー 1980=1987:214)
考察
セルトーとフーコー
近代的な再生産装置、それは我々をある地平へと送還する。ミシェル・フーコーの権力論は、つねにゼロ地点にあり、そこには概念的装置の諸相しかないものが、たえず肯定的に諸々を生産し続けている。そこに中心はなく、いわんや点もない。たえざる権力関係の移行が革命によってなされる際、それはすなわち装置としてのみ残存する大きな枠組みが新たな権力関係を生産することとなる。いっさいのものが清算されるわけではなく、ある形態を維持した状態で局所的な婚姻関係を解消することとなるからして、それは生産的な行為である。あたかもその様態は「クラインの壺」を彷彿とさせる。それは表と裏がなく、水でその内部を満たすことは出来ない為、転じて権力関係のいっさいを固定的なそれとして捉えることは不可能となるのだ。たえざる権力の転覆運動の末に、その壺はやはり三次元空間内において自己交差するのである(浅田 1983)。
壺の内で完結してしまういっさいの動的諸力の関係性とは、しかしながら局所的な闘争、そして逃走の場ともなる。ともすれば、それは主体である抑圧者による、客体としての被収容者への処罰の構造として捉えることは不可能となるだろう。ゆえに、局所的なイデオロギー装置である「パノプティコン」(フーコー 1975=2020)は、一対一対応的なものとはならず、「アレンジメント」(ドゥルーズ&ガタリ 1980=2010)を形成する。つまり、≪看守+囚人≫というものではなく、≪看守×囚人×パノプティコン≫という式になるのだ。観察者が身を置くある地点とそれに対応する監視対象の関係性は、緯度と経度によって割り出されるような、三つの点によって均質的かつ等質的に割り出されるような「条理空間」(ドゥルーズ&ガタリ 1991=2012)を描き出さない。
「条理空間」は、エレアのゼノンのパラドックスのように、空間を無限分割することが可能で、かつ時間を運動としてとらえてしまう誤謬を犯した。すなわちそのアキレスと亀の命題は、ゼノンその人によって監視されているからこそ、分割が可能なものとして矛盾を示してしまったのである。そうではなく、「絶対速度」(ドゥルーズ&ガタリ 1991=2012)として静止した運動をとらえることこそが重要である。その「速度を捉えるには、知性による抽象作用を超え、安全地帯から観察するだけの臆病さを投げ捨て、直接「この世界」の実在として在る平滑空間に身を曝し、自ら足を踏み入れそれにじかに触れようとする勇気と努力が必要とされるのだ」(大山 2016:10)。ここでいう「平滑空間」(ドゥルーズ&ガタリ 1991=2012)とは、まさしく≪看守×囚人×パノプティコン≫の状態のことであり、中心地点のない、フーコーの描き出そうとしていた「パノプティコン」なのである。
簡単にフーコーの権力論について説明しよう。フーコーの分析によって明らかになった権力は近代的なものであった。近代以前の権力は君主型のものであり、直接的な恐怖によって支配するやり方であった。すなわち、犯罪者を殺したり、いたぶったりする身体刑によるものだ。それゆえ、彼らは身体刑による暴力が、直接身体に恐怖を植え付けられたのである。ある種の見せしめは、そのような効果があったことだろう。
近代の権力とは、すなわち「規律権力」(フーコー 1975=2020)と「生権力」(フーコー 1976=1986)によるものである。「規律権力」とは、ベンサムの考案した「パノプティコン」を例にしてフーコーが説明したのは有名だろう。「パノプティコン」は、看守塔を囲むようにして囚人房が円形に配置されている監獄のことである。中央の看守塔は囚人にとって見えない。しかしながら、看守塔から囚人房の様子は一望することができる。それゆえ、この配置が可能にしたものとは、より少ない人数の看守によって、囚人のことを監視できるように設計されたものであった。
だがしかし、フーコーが示した効率性、それよりも優れているところは、囚人自らが己を監視するようになることにある。そこでは、看守はつねに見張っていなくてもよい。というのは、看守塔が囚人房から見えないことによって、囚人はいつ何時も見られていいようにするために自らを「規律訓練」(フーコー 1975=2020)させるのである。囚人は、看守の視線を内に取り込むこと、つまり規範を内面化することによって、自己の規律を訓練させられるのである。たとい、看守がいっさい囚人のことを現に監視していなくとも、囚人にとってはつねにみられているかのように錯覚するためにこうなるのだ。要するにそれは、「中心の不在そのものによって際立つような、非人称の監視システムとして描き出されるものである」(檜垣 2006:11)。
かつての見せしめによる処刑は、つまり身体に課される処罰であった。しかしながら、この「パノプティコン」のシステムが示すように、ミクロな個人を直接支配するようなかつての身体刑よりも、近代ではより間接的で効率的な方法として、自由刑への移行がされたのである。このような自由刑は、つまり囚人の身体の自由を束縛し、監獄という施設へと収容することによって、拘束を行うことによるものである。その目的意識は、恐怖を植え付けるものではなく、正しい規律にしたがった行動を囚人に押し付けるのである。それは支配者の意識を内面化させることによって成立する。はたして、恐怖によって直接的に支配されるやり方と間接的に意識を内面化させるやり方とでは、どちらがより残虐な方法であろうか。蓋し、後者の方は、他者の意識を内面化させるというならば、囚人自らの意識は徹底的に排除されてしまう点から、より冷酷非情なものではなかろうか。
もう一方の「生権力」は、ミクロな個人を支配する「規律権力」と違い、マクロな集団を管理する生政治なるものである。それはつまり、誕生、死亡率、健康水準、寿命、これらすべてを調べ上げ、時には介入したり、調整したりするような管理型の権力である。それはつまり、マクロなレベルでのコントロールであるからして、集団の生を管理するものなのである。これらはすべて数字によって管理されている。その数字が、なぜその値を示すのかを、支配者は一つ一つをまったくもって気にも留めないだろう。すべての生は、無機質なただの数字へと還元させられ、これに調整を加えることに対していっさいの躊躇がなくなるようなシステムとなっている。
ミクロなレベルでは、「規律権力」が、マクロなレベルでは「生権力」が、人々を監視・管理するようになった近代以降、とくに「規律権力」においては、なにも監獄だけに限られて作用しているわけではないのだ。重要なことは、この「規律権力」が、病院や学校などにおいても働いているのである。学校では、たとえば教師が前方の教壇に立ち、生徒がこの正面に座るようになっているのは、まさしくこの「パノプティコン」の配置を真似てのことである。また、生徒が座っている硬い椅子、決められたサイズの机は、彼らが手足をぶらぶらさせたりして、教室内で自由に動くのを防ぐための、足かせのような役割を果たしている。それは生徒に規律を内面化し、同時に数的に管理された学校用具によって身体の拘束を行うのである。フーコーはこれら二つの権力の綜合が広義の意味での「生権力」であると述べる。まさしくこれこそが近代を象徴する権力支配である。
しかしながら、このうちの「規律権力」はすでに時代遅れの短命な権力であったのだ。新たな権力は、コミュニケーションをあやつる「管理型」(ドゥルーズ 1990=2007)の社会であった。君主型・規律型は、それぞれの社会とそれぞれに対応する諸機械にタイプが存在するが、現代はこの管理型の社会にある。すなわち「管理社会の時代に差し掛かると、社会はもはや監禁によって機能するのではなく、恒常的な管理と、瞬時に成り立つコミュニケーションが幅を利かすようになる」(ドゥルーズ 1990=2007:350)のである。いまや管理という形によって成り立つそれは、つまりフーコーのいう狭義の意味での「生権力」に準ずるものである。わたしたちの生はつねに環境管理型の社会によって、行動が制限されている。これらはもっぱら、データに基づく数量分析に依存している。それゆえ、ミクロな個人の生はもはや興味関心が向けられず、ただ無機質な数字のみをミクロな個人から搾り取っているともいえよう。
ある意味では、わたしたちは自由な状態である。しかしながら真に解放されたと、そう思われていたはずの自由は、じつは数字の管理という形態をとって、私達の行動を制限していたのである。わたしたちは、不自由の刑に処せられている。自由だと思われていたものが管理されていたものであるならば、したがってわれわれはその主体的であったと思われた行動の諸相は、ただの共同幻想にすぎず、思い通りに動かされていたということになるのだ。
じっさい、私達は真の意味で自由となるとき、おそらく社会は何も手助けをしてくれないことだろう。私達はその意味で、つねにレディメイドの自由を享受しているだけの人生にこそすぎない。それどころか真の自由を手に入れた際には、どう行動すればよいかを知らない。そうしたときのために、大きな失敗を起こさないようにレールを引くことは、果たしてよい社会であるといえるだろうか。あるいはまた「管理社会」は、真なる自由という生の歓びを享受することはもはやできず、これらの活き活きとした生を奪い取り、われわれ人間の尊厳を内側から貪り食う凶悪な虫であろうか。
*
セルトーは、フーコーが明らかにしたその規律型の権力作用の分析を裏返したものである。マクロな意味での「生権力」ないしは、「管理型」の社会は、ミクロな個人を放し飼いしている。他方で、監視カメラなどのように、こんにちでも僅かに残存する「規律権力」はミクロな個人をより直接的な形で権力を行使する。個人を取り巻く非人称の装置としての「規律権力」は、しかるにどこまでも監視の目を緩めない。天網恢恢疎にして漏らさず、監視の網の目はどこまでも張り巡らされている。
だがしかし、そうは問屋が卸さない。フーコー自身が「規律社会」のモデルが短命であることをやはり知り尽くしていたように、現代では監視の網の目に囚われながらも、その中で隠密形態をとり、支配から逃れ続けている人々がいるのである。しかしながら、その監視の網の目はいまだに健在であり、単に暴力性が失われたというよりもむしろ、監視の網の目に囚われている人々の隠密形態が発展してきたのである。
フーコーにとっての権力は「戦略」(セルトー 1980=1987)であった。セルトーは、それとは対峙する人々のことを「戦術」(セルトー 1980=1987)的と述べた。以下の様に述べている。
また、逆だというのは、秩序の暴力がいかにして規律化のテクノロジーに変化してゆくかをあきらかにするのはもはや問題ではなく、さまざまな集団や個人が、これからも「監視」の編み目のなかにとらわれつづけながら、そこで発揮する創造性、そこここに散らばり、戦術的で、ブリコラージュにたけたその創造性がいったいいかなる隠密形態をとっているのか、それをほりおこすことが問題だからだ。消費者たちが発揮するこうした策略と手続きは、ついには反規律の網の目を形成してゆく。
(セルトー 1989=1987:18)
監視の網の目は確かに張り巡らされていて、その力はいまだに顕在であることは間違いない。しかしながらセルトーは、フーコーのように権力を明らかにするのはもはや問題ではないと切り捨て、フーコーの権力論を新たな側面から再検討したのである。
では、本当に監視の網の目はいまだに健在なのだろうか。セルトーにこの答えを求めるならば、然り而して否である。たしかに監視の網の目はある。しかしながら、「戦術的」に監視の網の目を逃走する彼らにとって、支配のコードに従順であるかのようにみせかけた隠密形態は、まさしく監視の網の目を伸縮自在に操ることのようである。だからこそ権力の不可視的な力は、かつてのそれに比べると弱まってきていることもまた事実だ。単に権力の力が弱まったというだけではなく、隠密形態がより発展してきている点も重要である。そこでの隠密形態は、日常的に行われる実践的なものであり、これからも権力作用に絡めとられながらも生きている主体的な駆け引きの場となり、「ブリコラージュ」(レヴィ=ストロース 1962=1977)に長けた、創造的で創発的な対抗文化の諸相を繰り広げているのである。
たしかに私達は、ある意味では不自由な社会に生きているといってもよい。しかしながら、そのなかでもたしかに私達は世界の中で生きており、かてて加えて、世界とともに生きている。それを単純に、抑圧的な構造を背景に見るだけでは、抑圧者と被抑圧者の関係性は、おしなべて一義的なものに結び付けられてしまう。そうではなく、これからもこうした社会に生きながらえつつ、それと共に「なんとかやっていく」ことこそが重要なのである。
まさしく、セルトーにとって、人々の日常的な営為は、俯瞰して見えるものではなく、街路に自らが出向くことによって見えてくるような、そうした見るという行為そのものであったに違いない。
セルトーの空間論
セルトーにとって、街路とは一つの「空間」(セルトー 1989=1987)であった。それは、「場所」(セルトー 1989=1987)と対置されるものである。「場所」とはつまり、ある土地が秘めている歴史的な出来事が込められる意味合いである。それは並列的に配置される固有の秩序だったものであり、一挙に与えられる布置である。つまり一義的な意味合いを「場所」は保有しており、まさしく欧州圏の固有名詞が付いた通りの名前は、その意味で歴史的な「場所」の点在である。その通りは、あるつけられた名前に由来するからして、出来事や人物名へと直接に結び付けられてしまう。
一方、「空間」とは、方向、速度、時間を「場所」に取り入れたものであり、動くものの交錯するところである。「場所」を通りゆく人たちには、何かしらの意味合いがそこには存在する。しかしながら、「場所」とは解釈をよしとせず、固有の意味合いを個人に押し付けるものである。そうでなく、その「場所」を通りゆく人は、多種多様な意味合いをもって、その場と関わることとなる。それは一義的なものではなく、意識はバラバラなのである。要するにこの多種多様な意味合いが交錯する場こそが、セルトーのいわんとする「空間」なのである。
日本社会においては、通りに固有名詞が冠せられることはあまりない。あるのは無機質な「国道○○号線」のようなものだけである。既存のものに軽く手を加えるのではなく、まさしくスクラップ・アンド・ビルドをする日本社会はなかんずく、都市からこの「場所」を忘却の彼方へと追いやってしまい、人はみなその通りを通るたびに特別な記憶をそこに思い馳せることはまずないだろう。したがって、「場所」がそもそもないのならば、やはり「空間」は存在しえないのかもしれない。
ところが、通りに「空間」の存在は認められずとも、「空間」はたしかに点在しているように思われる。私の通う職場は、様々な意味作用が揺蕩う交錯するさなかにあるような、さながら交差点のようなものである。アルバイトをするところ、仕事をするところ、過去に働いていたところ、いずれ去りゆくところ……、足繫く通う職場としての場所だけではなく、いつもの通学・通勤で通るところ、犬の散歩で通るところとそれぞれが、私にとっての職場に対して多様な意味合いを見出しては、そのひとつの「空間」と関りを持っているように思われる。そのかかわり方は、歩きながら、自転車に乗りながら、自動車に乗りながら、タクシーに乗りながら、バスに乗りながら、音楽を聴きながら、スキップをしながら、多様な価値の様態と動的な戯れが放射状に離散している。そこに統合的な動きはけっして見られまい。
私の通う学校には、「ホーチミン広場」(鈴木 2003)というものがある。当時の貧乏だった学生たちによる炊き出しがその場で行われていたのは、ベトナム反戦運動のときにまで遡る。大きなレンガ造りの竈は、その後も学生たちによって連綿たる思いで受け継がれていったようだ。OBの教員から偶然講義中に耳にしたその単語は、当時の私には存じ上げぬ異質なところであった。ところが、読書によって偶然の再会を果たし、はじめてその場所を知った。異質なところだったものは、どこか過ぎ去っていった過去のものを追い求めるという意味では「場所」であった。もはや、いまその「場所」を知る学生はほとんどおらず、すっかり「ホーチミン広場」と名付けられたその「場所」は、形骸化した場になってしまった。今ではポツンと置かれているベンチがあるが、それはその場に学生が屯することを阻止するための管理教育的なためだろうか。
ところが、コロナ禍から少し経ったいま、どこか虚しい場だった「ホーチミン広場」の周辺は活気を取り戻しつつある。それは、「ホーチミン広場」と称す立て看板が立てられてからのことだろうか。周辺の生協前の通りは、フリーマーケットをする者、募金をしている者、講義を行う/聴講する者、友人と立ち話をする者などがおり、さまざまな「空間」を形成している。「場所」は忘却するとどこか虚しい異質のものになってしまう。だがしかし、ちょうど「ホーチミン広場」の立て看板を設置するように、何かしらの意味合いを付与し、その場の出来事などを想起させる固有名詞が冠せられる場とはすなわち、「場所」となって、その場を日常的なものへと変容させることができるのだ。
あとがき
さて、本稿では第7章の要約とともに、歩くことを中心にあとがきを書いた。紙幅の都合上触れることができませんでしたが、「場所」と「空間」の話は第9章の空間の物語をぜひ読んでいただきたいです。
ほかにも本稿で触れた「ブリコラージュ」は、ありあわせのものでつくる日曜大工的な意味合いのものであり、クロード・レヴィ=ストロースが『野生の思考』で述べた概念です。過去にも買取日記で紹介されているように(【買取実績】文化人類学・歴史・言語学等書籍の買取 【81冊 7,535円】 || 古本・専門書の買取査定はノースブックセンター)、いまでも色あせない不朽の名作のひとつです。
また、こちらの記事で紹介されている(【買取実績】哲学・思想・宗教書籍の買取【518点 30,949円】 || 古本・専門書の買取査定はノースブックセンター)アーヴィング・ゴフマンの『アサイラム』は、セルトーが多分に参考にした研究でもあります(セルトー 1980=1987:20)。その調査対象者である精神病院の被収容者を描きとるゴフマンの分析は、たんに「全制的施設」の歪な規則や構造を糾弾するものではけっしてなく、支配を受け入れながらも、じっさいには監視の目を欺くことによって、主体性を確保する「第二次的調整」が行われます。たとえばちょうど、学校の生徒が授業中に落書きに真剣になり、しかしながら授業が終わると途端にお絵描きに興味がなくなるように、表面上は支配を受け入れつつも、その支配を逃れる動きが多分に見られることをえがきとった本作は、セルトーを読むにあたっては必携の本です。
さいごに、本書は当時から半世紀ほど経ったものの、つねに哲学諸分野がそうであったように、本書はとりわけ創造的な意味での誤読や本の使用の多数化が可能です。フーコーの分析の裏返しとしての読み方のみならず、空間論的転回としての読み方などもできます。また書き残してしまいましたが、セルトーのいう「日常」とはいったい如何様のものであったのでしょうか。
参考文献
Certeau, Michel (1980) L’Invention du quotidian. 1, Arts de faire, U.G.E
- ミシェル・ド・セルトー『日常的実践のポイエティーク』(山田登世子,1987,国文社)
Deleuze, Gilles (1990) Pourparlers : 1972-1990. Minuit
- ジル・ドゥルーズ『記号と事件:1972-1990年の対話』(宮林寛,2007,河出文庫)
Deleuze, Gilles & Félix Guattari (1980) Mille Plateaux : Capitalisme et schizophrénie. Minuit
- ジル・ドゥルーズ+フェリックス・ガタリ『千のプラトー 上:資本主義と分裂症』(宇野邦一、小沢秋広、田中敏彦、豊崎光一、宮林寛、守中高明,2010,河出文庫)
- ジル・ドゥルーズ+フェリックス・ガタリ『千のプラトー 中:資本主義と分裂症』(宇野邦一、小沢秋広、田中敏彦、豊崎光一、宮林寛、守中高明,2010,河出文庫)
- ジル・ドゥルーズ+フェリックス・ガタリ『千のプラトー 下:資本主義と分裂症』(宇野邦一、小沢秋広、田中敏彦、豊崎光一、宮林寛、守中高明,2010,河出文庫)
Deleuze, Gilles & Félix Guattari (1991) Qu’est-ce que la Philosophie ?. Minuit
- ジル・ドゥルーズ+フェリックス・ガタリ『哲学とは何か』(財津理,2012,河出文庫)
Foucault, Michel (1975) Surveiller et punir : naissance de la prison. Galimard
- ミシェル・フーコー『監獄の誕生:監視と処罰』(田村俶,2020,新潮社)
Foucault, Michel (1976) L’Histoire de la sexualité Ⅰ, La volonté de savoir. Gallimard
- ミシェル・フーコー『性の歴史Ⅰ:知への意志』(渡辺守章,1986,新潮社)
Lévi-Strauss, Claude (1962) La Pensée sauvage. Plon
- クロード・レヴィ=ストロース『野生の思考』(大橋保夫,1977,みすず書房)
浅田彰 1983『構造と力:記号論を超えて』勁草書房
大山載吉 2016『ドゥルーズ 抽象機械:<非>性の哲学』河出書房新社
鈴木勁介 2003『私編 岡上風土記稿』八月書館
檜垣立哉 2006『生と権力の哲学』ちくま新書
買取額は市場の需要と供給のバランスにより変動するため、現在とは異なる可能性がございます。上記は2025年10月時点の金額です。
ノースブックセンターでは、今回のように哲学をはじめ、心理学や思想等、社会学の専門書も積極的に買取しております。
整理をご検討の際は、ぜひ当店にご相談ください。
今回も良書をたくさんお売りいただき、ありがとうございました!
スタッフT
買取依頼をご検討の方は以下の「買取できるもの・できないもの」もご参照ください。
【買取品はAmazonの他、以下のサイトで再販いたします。】
【「一冊一善」寄付買取にご協力ください。】



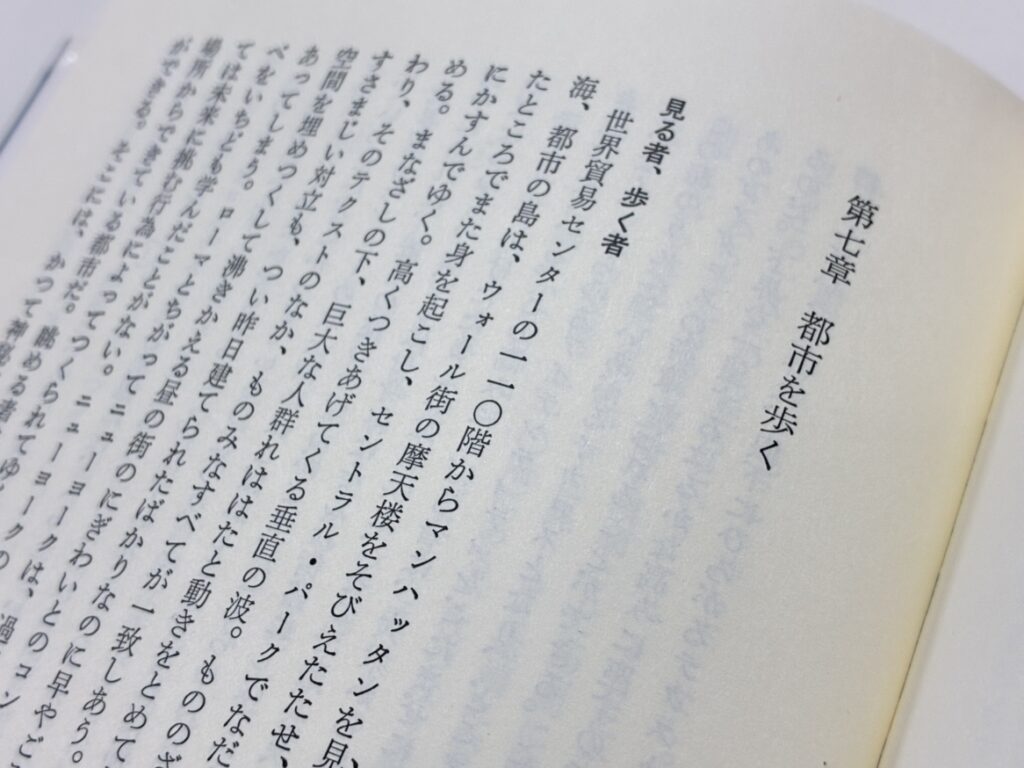
![日常という謎を生きる: ウルフ、小津、三島における生と死の感触
政治の美学: 権力と表象
現代演劇のフィールドワーク: 芸術生産の文化社会学
視覚と間文化性
フランスことわざ名言辞典 ([テキスト])
日常的実践のポイエティ-ク (ポリロゴス叢書)
ジンメル著作集 9 生の哲学
フランスの現象学〈新装版〉 (叢書・ウニベルシタス 911)
ハンナ・アーレント――〈世界への愛〉の物語
ヴェールのなかのモダニティ:ポスト社会主義国ウズベキスタンの経験
近代社会契約説の原理: ホッブス、ロック、ルソー像の統一的再構成
シェイクスピアの生ける芸術 (高山宏セレクション〈異貌の人文学〉)
ロゴスとレンマ
結婚観の歴史人類学
自己を超えて: ウィトゲンシュタイン、ハイデガー、レヴィナスと言語の限界 (叢書・ウニベルシタス)
友愛のポリティックス I
文化人類学文献事典
中世の幽霊――西欧社会における生者と死者
友愛のポリティックス II
丸山眞男集 別巻 新訂増補](https://www.northbookcenter-kaitori.com/wp/wp-content/uploads/2025/10/1760764441.png)